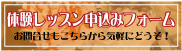|
当教室では、ストレッチから筋肉トレーニング、舞踊テクニカなど基礎に重点を置いています。 曲にのって振り付けを踊ることは楽しいことではありますが、踊りに必要な身体づくりをしないで踊りこみをすると、身体は悲鳴をあげ、故障につながります。 また、今まで気づかなかった潜在能力が突然開花してプロを目指す人もいますから、入門のうちから将来の役にたつよう、レッスン内容を考えています。 どうしてそのレッスンをするのか、稽古中だけでは語りつくせないことを、ここで具体的に解説しますので、これを読んで理解を深めてください。 ストレッチは、たんに身体に柔軟性をもたらすだけでなく、トラブル・故障の防止、技術の向上、筋肉の疲労回復にも大きな効果があります。 その効果1 トラブル・故障の防止
普段運動をしていない人は、筋肉が固く、故障を引き起こす可能性がかなりあります。 ある程度キャリアのある人は、踊りのレベルをアップさせるため、過度の練習量で思わぬ怪我をします。 私の経験では、肉離れ、捻挫、膝と腰痛です。 自分の故障した原因や周囲の話を探ると、筋肉と関節が固いことや、身体を冷やしたことが上げられます。 故障した後に後悔しても、痛い思いをするのは自分です。豊かな老後(?)を過ごすため、少しづつ、筋肉と関節を柔らかくしていきましょう。 その効果2 技術の向上
身体の柔軟性は、関節の運動可能範囲の大きさを指します。 関節の可動域が大きければ大きいほど柔軟性は高く、柔らかくてしなやかで美しく、切れのある動きができるようになります。 また、柔軟性に欠けていては、同じ動作でも柔軟性のある人より疲労度が大きくなります。身体の固さが動きの抵抗となり、余分なエネルギーが費やされるからです。 その効果3 筋肉の疲労回復
踊った後は、筋肉にストレスが残り、疲労や筋肉痛になります。これを解消、軽減するのに、柔軟ストレッチはかなり役に立ちます。 ストレッチは、疲れて固くなっている筋肉を伸ばすことによって血行をよくし、疲労回復を促進させます。就寝前に積極的にストレッチをしましょう。 ○ストレッチのポイント
◆呼吸はとても大切です。 息を吐くとき筋肉は伸びやすく、息を吸うとき筋肉は収縮することを覚えてください。 ◆ストレッチするとき、鼻から息を深く吸ってお腹を膨らませ、口から息をゆっくり吐きましょう。 ◆そして必ずリラックスした状態で行いましょう。 体が緊張していると、効果があがりません。 筋肉を伸ばして気持ちがいい状態でとめましょう。痛いと感じる人は、筋肉が硬直していますので、その筋肉をリラックスさせて、少しづつ柔らかくしていきましょう。 また、はずみをつけてストレッチをしないこと。筋肉が反射的に硬くなります。 ストレッチの姿勢は90秒以上が理想。 ◆ストレッチは、細心の注意を払って行う必要があります。 特に大人は、「急がば回れ」を心がけ、無理して伸ばして靭帯や筋を切らないよう気をつけましょう。 ◆頑張りすぎは禁物、やる気を理論的にコントロールしましょう。 リラックスして、不必要な緊張を取り除き、最良の筋肉のバランスをマスターし、もともと体が持っている知恵が花開くように努力を続けましょう。 |
  |
フラメンコを踊るのに筋肉トレーニングが必要なの?と驚かれた方がいらっしゃると思います。そう、必要です。 フラメンコは、日常では使わない筋肉をたくさん使って踊る特殊なものですから、日常で使わない筋肉を正しく使えるようにトレーニングしていきます。 柔軟性があっても筋肉がなければ、体は思うとおりに動いてくれませんし、故障の原因になりまし、何よりもフラメンコらしい踊りになりません。 スペインで有名な踊り手メルチェ・エスメラルダのクラスに筋肉トレーニングがあり、それをヒントにクラスで取り入れています。 筋肉は踊りだけでなく、毎日の生活のすべての動きに必要なものです。筋肉は使わないとどんどん衰えていき、衰えたそのレベルでしか力を発揮できなくなってしまいます。筋肉を鍛えるのは、きびきびした動きを保つため、傷害や痛みを防ぐ点からも大切です。 ○障害
筋肉がないことでおきる障害をふたつご紹介します。 1、腰痛症(筋肉性腰痛症)
踊りだけでなく、長時間の立ち仕事や椅子に腰掛けての仕事などで、腰の鈍痛を覚える人が多いようです。 腰を支える腹筋が弱くなると、いつも背骨の方に負担がかかり、疲労を起こして痛くなります。いわば筋肉のアンバランスによる故障ですので、運動療法としてストレッチ、腹筋を鍛えることが最も有効といわれています。 2、疲労骨折
足をささえる筋肉がないのに、過度に毎日サパテアード(足)の練習を繰り返すと、疲労骨折になることがあります。 これは、小さな力がある特定部分に何度もかかって骨が折れるもので、最初は症状がわかりづらく、病院で検査する頃にはひどくなっているケースが多いようです。 女性は年とともに骨密度が低くなってきますので、カルシウムなど栄養をきちんと取りましょう。 ○正しいトレーニング
筋肉は正しいトレーニングをしなければ、鍛えられません。以下、トレーニングの三大原則を守りましょう。 その1.特異性の原則
どこを鍛えたいのか、よく考えながら行うこと。 その2.オーバーロードの原則
日常の生活動作で使っているより大きな力を出さないと筋肉は強くならない。 その3.負荷の原則
徐々にトレーニングの負荷を上げる。 トレーニングの前後にストレッチをしましょう。 トレーニングは週2〜3日が理想です。週1日クラス受講の人は、自宅でも積極的にトレーニングをしましょう。 特に腹筋は日常生活ではほとんど使いませんので、毎日した方が効果的です。 他トレーニングの間は、1〜2日あけます。 腕立て伏せやスクワットなど、クラスでしている腹筋、背筋以外のトレーニングもした方が身体が軽くなりますので、おすすめします。 普段運動していない人は、まず必要最低限の筋肉をつけましょう。筋肉強化は基礎体力の向上にもなりますので、しんどくても頑張りましょう。 ●無酸素運動と有酸素運動
筋肉トレーニングのことを、無酸素運動もしくは等尺性運動(運動している間、力を発揮している筋肉の長さが一定のもの)といいます。トレーニング中、心拍数はそれほど上がりませんが、血圧が非常に上がりますので高血圧の人は注意が必要です。 これに対して、ジョギングやウォーキング、水泳、ダンスなどを有酸素運動といいます。トレーニング中、心拍数は上がりますが、血圧はそれほど上がりません。 これは心臓や肺の機能を向上させ、持久力、スタミナをつけることができます。また、血液の流れが促進され、毛細血管が増えるので、動脈硬化の進展をゆるやかにします。 つまり、踊るということは健康にとてもいいことなんです。 しかし効果があるのは、週2〜3日稽古をしている人です。 週1日の稽古ではそれほど効果がありませんので、そういう人はウォーキングや水泳なども積極的に取り入れて、健康的な身体を手に入れましょう。 参考文献: 女性のスポーツ事典(三省堂) ウエイト・トレーニング(同朋舎)他 |
   |
踊りで最初に学ばなくてはいけないこと、それは正しい立ち方です。 日ごろ、荷物を片側の肩ばかりかけたり、脚を同じ側ばかりに組んだり、寝そべってテレビをみたりしていると、身体は歪んできます。それに慣れると、歪んだ身体がまっすぐの状態だと錯覚してしまいます。 まず、身体を正確な美しい状態に保てるようにならなくてはいけません。 舞踊テクニカは、単純な動きをひたすら繰り返さなくてはいけないので、正直退屈だと感じると思います。美しい体をつくるには、この退屈な訓練を長く時間をかけて鍛えないと身につきません。ですから、注意散漫になったり、ぼうっと行っていては、思ったような効果や成果は得られません。 また、ある程度身体ができてきても、基礎を怠ると身体は確実に鈍ります。バレリーナがバーレッスンを毎日かかさないように、美しい踊りをするには、基礎テクニカは欠かせません。 気持ちを引き締めて稽古してください。 ○プリエとルルベ
プリエとは、フランス語で折り曲げるという意味で、単なる膝の曲げ伸ばしの動きとは異なります。ただの屈伸運動にならないように、ターンアウトしながら、股関節からふとももを外に向けさせ、太ももの前側の筋肉(大腿四頭筋)をなるべく使わず、太ももの内側の筋肉(大腿内転筋)を使うことを意識し、更に上体は天に向って引き上げ、下半身は地面を感じながら身体の中心を探ってください。 ルルベは、つま先立ちになることです。プリエ同様に、上半身は天に向って、下半身はつま先立ちでも地面を感じながら身体の軸を細く強くしていきましょう。 ○バットマン・タンデュ
(第3ポジションで足を前や後ろにだしたりするテクニカ) エクササイズする時、腰や肩が左右均等か、自分で確かめながらしましょう。 身体を正しいプレイスメントにしておくように、いつも努力しましょう。クラスでいい加減にやっていると、悪い習慣がついて、難しい振付を身につけることができなくなります。 自分に負けないよう心がけましょう。 ○ロン・ド・ジャンブ・ア・テール
(第3か5ポジションで足を前や後ろに半円を描きながらまわすテクニカ) これは、股関節を柔軟にし、腰の靭帯をゆるめ、身体の安定と、下半身が自由に使えるようになるための稽古です。 また普段私達は外側の筋肉で立ち歩きますが、舞踊は重心を内側にして軸を真ん中にしなくてはいけないので、この稽古で重心を真ん中にもってこれるようにしましょう。 エクササイズの動かすほうの足が半円を描いているとき、腰や肩が動かないよう、つねにまっすぐ立てるようにしましょう。重心は外側ではなく、内側にいくように心がけましょう。 ※用語解説 【ターンアウト】股関節を無理なく外旋させ、その外旋した股関節の方向と膝、爪先を必ず同じ方向に保ちます。 フラメンコは180度開く必要はありませんが、普段使っていない内側の筋肉を外に向けさせると、脚が美しくみえるようになるばかりか、安定感をもたらし、動ける範囲が広がり、スムーズにより強く動けるようになります。 ターンアウトで重要なのは、足先を外にむけるのではなく、太ももと股関節を外に向けることが重要です。膝の向きと足先の向きが必ず同じ方向に向くようにしましょう。そうでないと、膝を痛めます。 【第3ポジション】両足を腰から外側に開き、右足のかかとを左足の土踏まずに置きます。 【第5ポジション】両足を腰から外側に開き、右足のかかとは左足の親指の関節の前に置きます。 ●身体を理解しましょう
○バランスのみなもと:
脊柱(せきちゅう) バレエやダンスの要となるのは、手でもなく脚でもなく、脊柱といわれています。脊柱、つまり背骨です。動きを決めるのは、この背骨になります。 表現力を高めるのに、この背骨の使いかたは重要です。 ○バランスのコントロールセンター:
骨盤(こつばん) 安定性の主役は脊柱、それを支える土台は骨盤(こつばん)です。骨盤は、胴体や脚のあらゆる動きの中枢であり、踊りの姿勢と動きの中心です。 この骨盤と脚を結ぶ股関節の柔軟性は、あらゆるダンステクニックにおいて、とても重要です。 ストレッチ、舞踊テクニカともに、この骨盤を意識して稽古しましょう。 |
  |
○ブラソ(腕)
フラメンコ独特の動き、それはブラソでしょう。
ブラソとは、スペイン語で腕のことを言います。フラメンコはコンパスが一番大切ですが、ブラソとマノの使い方が悪ければ、観客に感動を与えることは難しいでしょう。 男性は、力強くキレのある動きで観客を魅了します。 一方女性は男性にない女性らしい美しい動き、繊細さが大切にされています。 このブラソは、女性には大変重要なので、時間をかけて指先まで感情が込められるように訓練をしていきます。 フラメンコが日本で流行り、今も尚人気がある理由のひとつに、年齢に関係なく踊れることがあげられます。 年とともに身体が衰えて若い頃のパワーがなくなってきても、アルテ(芸術)は年とともに磨かれていきますから、円熟のある踊りで観客を魅了することができ ます。素敵ですね。 そのためには、身体の使い方やブラソの基礎がしっかりできていないといけません。これは短時間で身につくものではないので、時間をかけて、自分のアルテ(芸術)を高めていってください。 最初はブラソの基本ポジションがきちんとできるようになることです。 まず、まっすぐ立ちましょう。ウエストから下の下半身は地に向かって、上半身は天に向かって身体をのばして立ちます。首は前に倒れてはいけません。まっすぐにあごを引いてください。 ブラソのポイントは、身体から必ず離して空間をつくってください。ブラソが脇や胸についてはいけません。 ブラソのラインは必ず丸みを持って、ヒジから上がり、ヒジから下げられるように、また肩が上がらないように気をつけながら、通るべきポジションを身体で 覚えましょう。ブラソは力をいれず、軽い感じでするということを意識してください。 基礎テクニカでしているブラソの基本は、応用のさまざまな動きで必ず使うことになりますので、無意識でも正しい基礎の形ができるように指先までしっかり 身につけましょう。 ○マノ(手)
マノの使い方の基本は、外回しと内回しの区別ができるようになり、手首がきちんと回ることです。フラメンコ独特の表現方法は、このマノの使い方で決まってきます。 指先は繊細に、コンパス感がだせるように意識してください。1本1本に神経を使い、間隔をあけながら曲げたりのばしたりできるように練習をしましょう。 ある程度できるようになってきたら、指先まで神経を使い、自分の感情を表現できるようになるまで、自分で研究してみましょう。 *この他に、サパテアードと呼ばれる足を打つテクニカ、ブエルタ(回転)、マルカールなどの基礎テクニカがあります。 これらの基礎をした上で、最後に振り付けをします。 |
ブラソ
 マノ
 |